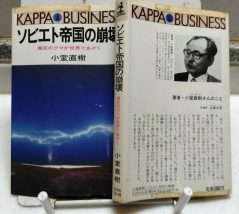
今回は、沖縄の歴史とは直接関係はないのですが、小室直樹著『ソビエト帝国の崩壊』(光文社)の一節を紹介します。同著第1章第3節「中世意識のままのソ連労働者」(51~59㌻)からの抜粋ですが、資本主義社会とそれ以前の社会における労働者の意識の違いを分りやすく説明しています。我が沖縄における廃藩置県以前の労働者の行動様式を理解するうえでのもっとも参考になる一節ですので、読者のみなさん是非ご参照ください(文章のなかに現代にはなじまない表現が一部ありますが、今回は訂正せずに原文をそのまま書き写しました)。
産業社会の労働には、二つの要素がなくてはならない
これまで述べてきたような経営的特徴を反映して、ソ連の労働者の労働態度もまた、資本主義社会のそれとくらべると、著しく劣ったものとなっている。
そもそも資本主義経済の労働の特色は、その一様性と規律性とにある。前資本主義時代とはちがって、労働者は働きたいときにやってきて、勝手に働けばよい、というものではない。一定の決められた時間と規律に従って、プランどおりに働く。
気違いのように働いたり、勝手に休んだり、ムラがあってはならないのである。そうでなければ、企業は労働を合理的に組織化し、効率的に使用することができない。
ところが、ソ連の労働者には、この規律性と労働力投入の一様性がみられないのである。
「だれもが働いている以上、こうした事情は全国民がよく知っている。というわけで、ふつう家庭用品を買うとき、その製品が月の十五日以前に製造されたという証明のあるものを買おうとする(ソビエトの品物には生産日時を示すラベルがついている)。もし、その品物が十五日以前につくられていれば、あわててつくられたものではないことがはっきりしている。客は”たぶん、これなら動くだろう”と考える。十五日以後だとすぐにこわれる可能性が高い」
– 彼は十七歳のとき、年長の労働者から旋盤の操作を教わった際、どうしてもっと早く操作できないかとたずねた。「できるけど、そのことは黙っている。来月からノルマを改訂されないよう、わざとゆっきりやってるんだ」(『ロシア人』前出より)
これでみると、ソ連の労働者は、社会主義的であるというよりは、むしろ前資本主義的にみえる。換言すれば、前産業社会的なのだ。
このことを理解することは、ソ連経済を理解する一つの鍵になると思われるので、少しくわしく説明しよう。
マルクスの学説によれば、社会主義経済は、資本主義経済の後にくることになっている。ソ連は社会主義の最たるものだと考えられている。しかし、ソ連の労働者の行動様式は、資本主義社会以前のものである。
これは、いったいどうしたものなのだろう。
ところで、産業社会という言葉を使ったが、これは、資本主義社会と社会主義社会とを一括したその上位概念、つまり、より一般化した考え方である。マルクスをはじめとする社会主義者の説を聞くと、社会主義経済と資本主義経済とは根本的にちがう、という。つまり、彼らは両者の相違点を強調するのである。
もちろん、そういう側面も重要であるにはちがいないが、他方、資本主義社会と社会主義社会とは多くの共通点をもち、それ以前の社会 – これを前産業社会という – とは、多くの点において著しく異なっている。
そこで、産業社会として社会主義社会と資本主義社会とをひとまとめにして考え、前産業社会と対比させながら分析するという視点も、重要になってくるのである。
では、産業社会の特色は何か。それは、
(1)労働力が、特定の目的のために、合理的に組織化されていること。
(2)労働の行動様式が確立していること
であり、このことこそ、産業社会をそれ以前の社会から決定的に区別する点なのである。現代のソ連にはこれが決定的に欠如している、とこれから述べるのだが、それにさきだって、これら二点について明らかにしておきたいと思う。
生産性が倍になると、半分しか働かなくなる人びと
労働力が、特定の目的達成のために合理的に組織化されていること、このことこそ、産業社会が成立するための必要条件である。前産業社会では、多くの場合、労働者は伝統的生活を保持するために働くのであり、特定の目的達成のために働くのではない。
こんな話がある。アメリカの有名な経済学者、アルヴィン・H・ハンセン教授がインドへ行って、あるコミュニティの改革にたずさわったことがあった。彼の努力によって、生産力は二倍になった。そこで彼は、このコミュニティ住民の生活水準はおそらく二倍になるだろうと考えた。アメリカ人ならば、当然の考え方である。ところが、そうではなかった。翌年、彼がもう一度行ってみてびっくりしたことには、このコミュニティの生活水準は、もとのままであった。びっくりしたハンセン教授がよく調べてみると、なんと彼らは、半分しか働かなくなったのである。
このように、前産業社会における労働者の関心は、伝統的生活水準を維持することにのみあり、効用の最大にはない。
こんな労働者を、企業の利潤最大のために合理的に組織化することは至難の業である。こんな労働者は、伝統的な好みに応じて、ともかくも働きこそすれ、企業トップの命令一下、アセンブリー・ラインにならんで、その労働力を合理的に組織して、与えられた目的達成のために突進するということは考えられないであろう。
ところが、産業社会においては、労働者の合理的組織化がなされ、企業利潤の最大化をめざすことが可能だ。それが産業社会の大原則なのだ。
これは、もちろん資本主義社会の話だが、事情は社会主義経済でも同じでなければならないはずである。社会主義経済でも、労働者は合理的に組織化され、特定の目的達成のために用いられなければならない。この点では、資本主義社会とまったく同様である。
ただ、資本主義とちがう点は、資本主義の場合には、組織の主体が私的企業であり、その目的が利潤の最大化であるのに対し、社会主義の場合には、組織の主体は国家であり、その目的は与えられたノルマの達成である点である。両者の違いは、これにつきる。他はまったく同じであるはずなのだ。
働くことが尊敬されない社会の労働者たち
次に、労働の行動様式(エトス)の話をしよう。
ここにいうエトスとは、じつは術語(テクニカル・ターム)であり、説明を要する。エトスとは、簡単にいえば、行動様式と、それをささえる心的態度のことをいう。倫理と訳されることもあるが、それよりも、もっと広いのである。もちろん、エトスは、倫理をその特殊場合として含むのであるから、時と場合によっては、倫理という意味で使用されることもある。ここでは労働のエトスの確立の話をするのだが、このさい、とくに重要なことは、”労働の規範化”であるので、これを中心に話をすすめたい。
”労働の規範化”とは、人間生活のなかで、「労働はたいへんよいことで、いちばん重要なことだ。」と認識され、いかなる労働をするか、ということによって、人間が評価されるようになることをいう。
といえば、こんなことは、あまりにもあたりまえのことで、今さらことあらたまって主張する必要のないことだ、と思うだろう。ところが、これがあたりまえなのは、じつは、資本主義や社会主義などの産業社会での話であって、それ以前の社会においては、必ずしもそうではないのである。
社会主義社会においては、労働は神聖なりといい、働かざるもの食うべからず、という。資本主義社会においては、いそがしい人、ビジネスマンは尊重され、ひまな人というと、けなし文句である。人は、その従事する職業によって評価され、ある人の威信とは、じつは、その人の職業威信にほかならない。
私の友人にこんなのがいた。彼は大金持ちで絵かきである。絵のほうはたいしたことはないが、それでも一応芸大を出ている。たいへんなプレイボーイでもある。職業はというと高校の教師。ところが、教師の給料など一晩でのんでしまう。それほど彼は金持ちなのだ。それならば、いっそのこと、教師などやめてしまってプレイに専念したほうがよさそうだが、そうはいかない。いくら金を持っていても、なんの職業にもついていなければ、世間では相手にされない。おつきあいをしようにも女の子が寄ってこないそうである。
これが産業社会というものである。アメリカでも同様であろう。ところが、前産業社会的エトスが残っているラテン・アメリカとなるとそうではない。
メキシコやブラジルのプレイボーイともなると、日本やアメリカなどでは想像もできない本格派だ。親父が一生かかってためた金だ、おれは一生かかって使ってやるとばかり、何の職業にもつかず、朝から晩まで遊び暮らす。日本やアメリカなら、こんな人間はたちまちだれからも相手にされなくなってしまって、早晩、遊びにもこと欠くようになってしまうのは必至なのだが、そこはまだ労働のエトスの確立していないラテン・アメリカのこと、これでも、いっこうにさしつかえはないのである。なにしろ金はあるし、だれにも迷惑のかかることではない。けっこう、人々の尊敬もあつめ、女の子にはすごくもてる。
本質的にいって、メキシコ人などこの類だろう。メキシコにいって驚くことは、何もかもアメリカ資本に占拠されてしまっていることだ。着てるものもアメリカ製なら、食料品もアメリカ製、自動車も家も、レジャー施設も、勤める会社もアメリカ系、そんなありさまだから、日本人だったら、とても我慢はできない。悲憤慷慨して、アメ公出てゆけと、あばれることだろう。ところが、メキシコ人はいっこうに碧なのである。
いわく、アメリカ人て、なんて非文化的なあわれな人種なんだろう。あんなに、朝から晩まで働いて、それで何になるんだろう。それにくらべるとメキシコの文化は高い。テキーラ酒でもたのしんで、興がのれば一晩おどり狂う。きれいな女の子がいれば窓の下でギターをひく、これが文化じゃないか、と。
日本でも、平安時代においては、美の追求が最高の人間活動であり、労働などは、いやしむべきものとされてきた。兼好法師にせよ、鴨長明にせよ、その生活基盤が何であったか、いまだに判明しないのであるが、そこが、みやび人のよい点だとされた。すなわち、ビジネスマンでなく、アイドルマンが人びとの理想であったのである。
西洋社会においても事情は同様であって、プラトンの共和国においては、人間活動のうち最高のものは”哲学をすること”、思索にふけることであり、次は、戦争をすることである。労働は、たかだか第三位にすぎない。
これが中世になると、人間活動の最高のものは”祈ること”になる。これは、日本も西欧も変わらない。カトリック修道院のように”祈り、かつ働く”ということが規範化されることもあっても、それはむしろ例外である。カトリックの場合には、修道院の中と俗人とでは、その守るべき規範のうえで著しいちがいがあるのを常としていた。修道院の中の労働のエトスが、世俗的禁欲として修道院の外に持ち出されるのは、マックス・ウェーバーも論じているように、プロテスタンティズムの倫理を媒介としてであった。
さて、このような労働のエトスが成立すると、これが産業社会成立の必要条件である。とすれば、ソ連における労働のエトスは、中世的、前産業社会的といわざるをえないし、そんな労働者によって真の産業社会がつくれるわけがない。
この節の最後をいささか皮肉な言葉でしめくくろうと思う。それは、ソ連がマルクス主義の国になったことは、日本にとって、たいへん幸せなことだったのではないか、ということだ。巨大な国土、資源にめぐまれた彼の国は、本来、日本の産業のたいへんな強敵のはずなのに、みずからの内部矛盾により、その潜在力をまったく生かせないからだ。