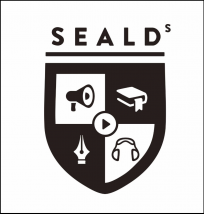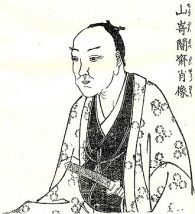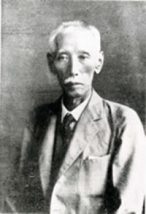昨日(12月22日)の Facebook に下記の投稿がありました。投稿者は棚原勝也さん、22日に行われた米軍北部訓練状の返還式に関するコメントのようです。
続・琉球藩の時代 クズエピソード再考
今回、琉球藩の時代の連載を再開するにあたって、過去の記事を読み返しましたが、やはりクズエピソードの部分が強烈な内容になっています。これらのエピソードは「沖縄県史」や比嘉春潮著「沖縄の歴史」、あるいは真境名安興著「沖縄一千年史」などからの抜粋ですが、現在の歴史教科書では余り取り上げることがありません。〈琉球・沖縄は薩摩の侵略以来ずっと差別されてきた〉という歴史観が、これらの事実に目を閉ざす最大の理由になっていることは間違いありません。
突撃グルメレポートシリーズ~フジヤマドラゴンカレーに行ってきたよ。
昨日Facebook上で、たまたまフジヤマドラゴンカレーのオープンキャンペーンの投稿を見ました。カレー680円がワンコイン500円でお得とありましたので、仕事が速く終わったのも幸いして、フジヤマドラゴンカレー沖縄国際通り店へ突撃しました。ブログ主はインスタントカレーなら200銘柄近く、スーパーのカレー販売棚の有名銘柄はほとんどすべて制覇した実績がありまして、カレーにはちょっとうるさ型です。ではフジヤマドラゴンカレーへのグルメレポートをアップします。
続・琉球藩の時代 プロローグ
今回の記事から、琉球藩の時代の連載を再開します。まだ公同会事件(1896~1897)のまとめ記事が残っているのですが、平行してブログ内にアップします。
その前に、以前当ブログ内にアップした琉球藩の時代の記事を改めて読み直して、いくらなんでもご先祖様のことをボロクソに書き過ぎじゃないのかと反省し、その後数多くの琉球・沖縄史や史料などを参照しました。そして出た結論が「もっとボロクソに書いていいいんじゃね」という……
公同会運動の顛末 失敗の本質 その2
前回の記事において、琉球沖縄の歴史では遂に尚家の存在を絶対化するイデオロギーが誕生しなかった件を指摘しました。よく考えると当たり前のことで、1609年(慶長14)の慶長の役の敗戦の結果、戦勝国である薩摩藩の要請で、王家が存続された歴史がある以上、そんな都合のいい基本思想が生まれる訳ありません。
公同会運動の顛末 失敗の本質 その1
今回からは公同会運動の失敗について、ブログ主が大胆な仮説をもとに検証します。この運動に関しては、今まではネガティブな印象が強かったのですが、実際に調べてみると実に面白く、そして廃藩置県後の沖縄社会の変遷を理解する上で格好の素材であることが分かりました。この運動がなぜ失敗したかについて、これまでの歴史教科書等では「復古的」「旧士族の最後のあがき」などで簡単に片付けられているケースが多く、正直ちょっと勿体無い気がするので、ここはブログ主が調子に乗りまくって失敗した理由を検証します。
公同会運動のきっかけは、沖縄県庁をはじめ当時の社会が他府県人に牛耳られていることに対する不満です。県庁の職員だけでなく、甚だしきは学校の先生や、警官までが県外人主体になっている有様です。しかも鹿児島県人の抜擢が著しく、当時の沖縄県人、特に留学帰りの新知識人が社会の現状に不満を持つもの無理はありません。
ただしこの運動の面白さは
公同会運動の顛末 琉球新報社が果たした役割 その6
前回の記事で、琉球新報社の伝統は社員たちのエリート意識にあることを説明しました。ここでのエリートとは、現在の学歴エリートやスポーツエリートの意味ではなく、「自分は使命を全うするために生まれてきた」ことを自覚した人のことを指します。言わば太田朝敷氏らの初期の琉球新報の社員たちは、日清戦争の結果後にエリートとして生きることを宿命つけられたのです。
公同会運動の顛末 琉球新報社が果たした役割 その5
前回までに沖縄タイムス社に対するブログ主の仮説を掲載しました。今回からは本題である琉球新報社が沖縄社会に対して果たした役割について述べます。
琉球新報社は前述の通り、1893年(明治26)に奈良原知事の提案と尚家がスポンサーになって設立されました。その経緯ゆえに機関紙的な性質が極めて強い新聞社だったのですが、日清戦争(1894~1895)の結果、新報社は社風の変質を余儀なくされます。
公同会運動の顛末 琉球新報社が果たした役割 その4
前回は、公同会運動とは直接関係ない沖縄タイムスの沿革について記述しました。せっかくの機会なので、この場を借りて沖縄タイムスがなぜ偏向とまで呼ばれるような論調を記載し続けるか、ブログ主なりに整理しましたのでご参照ください。
沖縄タイムスは伝統的に既存の権威や権力、および社会的勢力に対して徹底的に距離を置くスタイルです。それ故に旧革新勢力(現オールおきなわ)や市民団体等よりの記事が目立ちますが、理由は
公同会運動の顛末 琉球新報社が果たした役割 その3
今回はついでと言っては何ですが、沖縄タイムスの変遷について掲載します。県下最大の新聞社ですが、現在では何かと評判がよろしくありません。若い世代からはその論調が目の敵にされている傾向すらありますが、沖縄タイムスの出自を振り返ると、納得できる所もありますので、ブログ主が調子に乗って社の変遷を説明します。
沖縄タイムスは1948年(昭和23)7月1日に創設されます。設立時のメンバーは戦前の「沖縄朝日新聞」のメンバーを中心にスタートしますが、琉球新報との違いは
公同会運動の顛末 琉球新報社が果たした役割 その2
前回の記事では、1893年(明治26)に誕生した琉球新報について説明しました。今回は1951年(昭和26)9月に「うるま新報」から「琉球新報」に改題した現代の琉球新報社について記述します。
実は現代の琉球新報社は、大日本帝国の琉球新報社の伝統を完全に引き継いでいません。理由は
琉球新報ほか沖縄のマスメディア関連の資料
琉球新報ほか、沖縄のマスメディア関連の資料を掲載します。
※令和05(2023)年1月19日、一部記事を削除し、関連リンクを挿入しました。あと読者の弁を図るべく、記事レイアウトも変更済です。今後、沖縄マスメディア関連の資料は、新規の記事として当ブログにてアップするのでご了承ください。
公同会運動の顛末 琉球新報社が果たした役割 その1
前回までは公同会事件における頑固党と、現在のオールおきなわの勢力との比較を記事にしました。時代も主義・主張も違えど、驚くほどの共通点があったのですが、今回からは琉球新報社の古今比較を記事にします。
公同会事件において琉球新報の果たした役割は非常に大きいものがありました。公同会運動の特徴は
新しいPCが届いたでござるの巻
今回の記事は少し気分を変えて、先日注文したWindows 10のノートPCのセットアップレポートを掲載します。
購入したのはASUS製のTransBook Mini T102HAで10.1インチ型、タッチパネルとスタイラスペンがついて5万強のお買い得な商品です。持ち運びに便利なセカンドPCとして購入しましたが、実はひとつ前世代のTransbook T100HAが実に呪われたアイテムだったのです。T100HAシリーズはバカ売れしたと聞きますが、ブログ主が去年9月末に購入した機種は初期不良2回、修理3回という神っているとしか言いようがないほどトラブルに見舞われました。ちなみに現在4回目の修理対応中です。
公同会運動の顛末 頑固党とオールおきなわ その3
前回の記事はすこしキツい内容になりましたが、歴史を振り返って現代のオールおきなわ(旧革新勢力)の行く末を考えると、答えはただ一つ「没落」しかありえません。理由は彼らの思想・心情を後世の沖縄県民が引き継ぐとはとても思えないからです。
その前に「没落」の意味を説明します。公同会事件後(1896~1897)に頑固党は沖縄社会における影響力を完全に失います。彼らの家禄は1910年(明治43)まで明治政府が保証したため*生活に困ることはありませんでした。ただし琉球士族のプライドは粉々に砕け散り、頑固党の子孫はすべて日本人になることで士族の伝統は完全に断ち切られることになったのです。(例外は尚家)