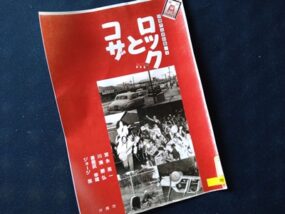今回は番外編として謝名もい〔zanamee:ヂァナメー〕こと察度の伝説について考察します。今回取り上げるのは察度が勝連按司の娘を娶る物語ですが、ちなみにこの話の初見は羽地朝秀著「中山世鑑」です。つまり17世紀の意識高い為政者が、りうきうの伝説をどのように解釈していたかを知る貴重な内容と言えますが、先ずは物語の大意を紹介しますので是非ご参照下さい。
人物
阿麻和利の謎 – 肝高(1)
今回は勝連の対語である「きむたか」について言及しますが、その前におもろさうしの対語表現について説明します。
おもろさうしでは対語が多数見受けられますが、これは「同じ言葉をくり返し使わない」という理にかなった文学表現です。ちなみにおもろそうしの対語表現は、最初に人名(あるいは地名)を唱え、別行で性質や特性を表記するケースが多く、たとえば首里森(首里城のこと)の対語は真玉森であり、意訳すると「美しい首里王城」になります。
阿麻和利の謎 – 勝連(2)
前回の記事で、かつれんの方言読み(カッチン)から、ブログ主なりに語源を考察してみましたが、実際に勝連城跡を訪れた際に、謎があっさり解けた感を覚えました。確かにあの場所は「古りうきうの住民たちにとって神の恵みを実感できるところ」で間違いないのです。
阿麻和利の謎 – 勝連(1)
今回から数回にわたって「勝連」の名称についてブログ主なりに考察します。というのも「おもろさうし」に登場する「かつれん」は二つの意味を含んでいることに気が付いて、強い興味を抱いたからです。
阿麻和利の謎 – 番外編(2)
前回の記事において、おもろさうし巻10「ありきゑとのおもろ御さうし」にあるりうきう開闢のオモロについて言及しましたが、今回は「中山世鑑」に掲載されている天地開闢物語との違いについて深堀します。
阿麻和利の謎 – 番外編(1)
今回は阿麻和利の謎の番外編として、おもろさうしに掲載されているりうきう天地開闢のオモロについてブログ主なりに解説します。というのも古りうきうの神観を伺うにはこのオモロは格好の史料だと確信しているからです。ただし非常に長く、わかりにくいオモロでもありますので、今回は大意と解説を先に、そしてオモロ本文は最後に掲載しますのでご了承ください。
阿麻和利の謎 – 聖名(2)
前回の記事において古代りうきう社会における「聖名」について言及しましたが、今回は「あまわり」の名称について考察します。鳥越憲三郎先生はあまわりの語源を「天降り」であると主張していますが、この点はブログ主も完全同意です。
阿麻和利の謎 – 聖名(1)
前回の記事において、ブログ主は阿麻和利の呼称について、俗名ではなく「聖名」であると仮定しましたが、今回は古代りうきう社会における権力者の「聖名」について説明します。
阿麻和利の謎 – プロローグ
6月22日から絶賛開催中の第106回全国高等学校野球選手権沖縄大会(以下夏の沖縄大会)も終わり、高校野球の熱狂から少しづつ冷めつつあるブログ主ですが、今月から(試験的に)定期連載として「阿麻和利」に関する記事の配信を行います。
ロックとコザ(1994)川満勝弘(愛称:カッちゃん)編 – その32
(続き)例えば、私たちのおじいちゃん、おばあちゃんの、そのまたおじいちゃん、おばあちゃんたちが味噌汁を食べてたという歴史があって、朝はパン食にするにしても、どうしてもゴーヤーチャンプルー(ニガウリの炒めもの)というものが沖縄にある、食べたことないけどあるんだというのはわかるわけです。こういう味噌汁の余韻というのがあるわけです。おかず、漬物というのがまだ残っているわけです。
ロックとコザ(1994)川満勝弘(愛称:カッちゃん)編 – その31
□音楽の現状とルーツ こういうアメリカの若者を相手にしているから、ロックをやっていると、アメリカでは音楽のどこを大事にしているということがすぐダイレクトに伝わるし、そういう基本的なものがわかってくると、こことこことここの三つを大事にすればだいたいのものは、あとは時間が経てばマスターできるものだというのがわかるんです。これを見失って枝葉だけのものを仕上げていっても、アメリカでは通用しないというのが実状です。
ロックとコザ(1994)川満勝弘(愛称:カッちゃん)編 – その30
(続き)また、むこうはまともな英語で沖縄へ来たんですが、私とつき合っている間にブロークンイングリッシュになってしまい、本人が気づかないということもあります。それで他の人から「おいマーク、おまえ、What kind English you speaking(おまえどんな英語を使っているの?)といわれたりするわけです。「Why? (どういうこと)」、「Your 〔language〕 is fany? You think so? (あなたの言葉は変だよ、そう思わないの)」という具合に、私と話したから、アメリカに帰っても、こうしてブロークンイングリッシュにしないと話せなくなった人がたくさんいます。
ロックとコザ(1994)川満勝弘(愛称:カッちゃん)編 – その29
□音楽への取り組み方 普通のミュージシャンは、あーしよう、こうしようと練習をやるんですけど、私の場合はやらなさすぎるんじゃないかな。私の場合は、なんかやっても無理というか、練習やったらその練習したものが崩れていくから、「あんたはもう練習しない方がいい」とみんなからいわれるんです。
ロックとコザ(1994)川満勝弘(愛称:カッちゃん)編 – その28
□中野サンプラザでコンサート これは東京でデビューするときの話です。
一九七七年八月にはじめて「中野サンプラザ」でデビューコンサートしたとき、蛇を食いちぎるバンド、ステージに女の人を上げてレイプするバンドとか、男のチンチンを切るバンドとか、鼻からタバコ、ビールいろいろ、とにかくたいへんだといって、ハードロックの超ハードロック、日本、東京上陸と週刊誌にも報道陣にもう騒がれ過ぎるくらい騒がれました。
ロックとコザ(1994)川満勝弘(愛称:カッちゃん)編 – その27
(続き)すると、マネージャーは「いや上がってる」と怒っているのです。それで私も機械を見て上がっていたので「私じゃない、彼(ミキサー)。彼にいってよ、僕にいわないで。何でいつも僕の顔を見ていうのあんた。僕が大きくしたわけじゃないよ、大きくしたのはあの人」というと、