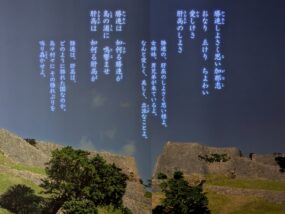前回の記事において、阿麻和利時代に港として利用されていたとされる “浜川” を拠点とした外洋貿易は無理であると述べましたが、今回はその理由について言及します。
人物
勝連城跡の謎 – 航海
前回の記事において、勝連城跡で使用された瓦は船で輸送された可能性について言及しました。では「どこから持ってきたのか?」を考察する前に、16世紀以前の勝連における海運について考察します。
勝連城跡の謎 – 瓦
これまで「おもろさうし」から見た勝連の実力について考察してきましたが、それはあくまで中城や越来との比較であって、古代社会における勝連半島の地域が経済的に貧相だった裏付けにはなりません。その傍証として勝連城跡からの出土品から、それなりの財力を備えていたことが分かります。
「おもろさうし」から見た勝連の実力(五)
前回の記事において、「勝連は、何にか譬へる(以下略)」は祭式オモロであった可能性について言及しましたが、今回はこのオモロを唱えた人物について考察します。ちなみに「おもろさうし」では題字と唄(オモロ)の関連性が謎めいており、「なぜこのオモロにこんな題字がついたのだろう」と思わざるを得ないオモロが多数ありますが、そのあたりの限界を考慮した上で、「作者」について考察します。
又吉世喜さんについて知っていること(2)
前回アップした記事「又吉世喜さんについて知っていること。」に関し、今回は裏付け史料を公開します。又吉に関してはブログ主が所持する史料から昭和38年(1963)までは正確に追跡できるので、数多くの史料から彼の “実像” に迫る内容のものを厳選して公開します。
「おもろさうし」から見た勝連の実力(四)
前回の記事において、ブログ主は「勝連は、何にか譬へる(以下略)」の有名なオモロは、祭式オモロであると仮定しました。
ここで祭式オモロについて定義すると、過去に神託として下されたオモロがテンプレ化され、後世の祭儀に用いられるようになった類のものであり、「おもろさうし」には巻三「きこゑ大ぎみがなしおもろ御さうし」に集録されている64のオモロの、実に32首が祭式歌謡として用いられています。
「おもろさうし」から見た勝連の実力(三)
今回は古りうきう時代における勝連の繁栄の証として引用されるオモロについて深堀します。伊波普猷先生の『古琉球』の阿麻和利考によって有名になった「かつれんはなおにきやたとへる」から始まるオモロですが、実は伊波先生と鳥越憲三郎先生の解釈がだいぶ異なっています。
「おもろさうし」から見た勝連の実力(二)
前回は「おもろさうし」から中城の国力について言及しましたが、今回は極めて興味深いオモロが掲載されている越来について言及します。実は越来のオモロは中城と違い “王者” を連想させる語句が使われているのが特徴です。
「おもろさうし」から見た勝連の実力(一)
今回から数回にわたって「おもろさうし」から見た勝連の “実力” について考察します。具体的には他の地域(中城・越来)のオモロと比較することで、勝連の国力を推測していくわけですが、その前に「おもろさうし」に登場する “神” についてまとめておきます。
阿麻和利の乱(五)
前回の記事において、第二尚氏以降も勝連城主は「阿麻和利」を名乗っていた可能性に言及しましたが、今回は詩人である「おもろ殿原」について深堀します。
巻八「おもろねやかりあかいんこかおもろ御さうし」におもろ音上がり(オモロ詩人)のオモロが43首集録されていますが、彼(あるいは彼ら)のオモロには女神官のオモロとは違った特色があり、具体的には「国王、按司、民」を強く意識したオモロが散見されるのです。
阿麻和利の乱(四)
前回の記事において、古りうきうにおける勝連と首里との関係が伺えるオモロを紹介しました。そして今回紹介するオモロが決定打になりそうですが、実はこのオモロは鳥越先生の解釈に(唯一)納得いかなかった難解な内容となっています。
又吉世喜さんについて知っていること。
ご存じのとおり、今年は昭和に換算すると100年の節目ですが、”スター” こと又吉世喜さん(1933~1975)がお亡くなりになって50年目であることを知る人は少ないかと思われます。そこで節目の年の企画として、又吉(以下敬称略)に関するまとめページ作成を思いつきました。
阿麻和利の乱(三)
今回から「おもろさうし」から首里と勝連の関係について言及しますが、実は勝連のオモロにはおぎやかもい(尚真王)を讃える内容の唄があります。それ故におもろさうし編纂時に、王家に都合の悪いオモロはカットされたのではとも考えられます。
阿麻和利の乱(二)
前回の記事において阿麻和利の乱を「史実認定」すると、どうしても不都合が生じてしまうこと、そして当ブログでは18世紀以前の史料、具体的には「おもろさうし」から首里と勝連の関係について推測する旨言及しました。100年以上前に偉大なる伊波普猷先生が試みた手法を採用するわけですが、伊波先生とブログ主では少し立場が違います。今回はこの点について説明します。
阿麻和利の乱(一)
今年の8月から当運営ブログにて定期連載してきた “阿麻和利” について、今回から彼が起こしたとされる反乱について考察します。
現在の我が沖縄において、護佐丸・阿麻和利の乱は15世紀の半ばの史実として認識されていますが、その傍証としてGrok(XのAI生成ツール)に「阿麻和利の乱について教えて」と尋ねた際の回答がなかなかの出来栄えだったので全文を紹介します。