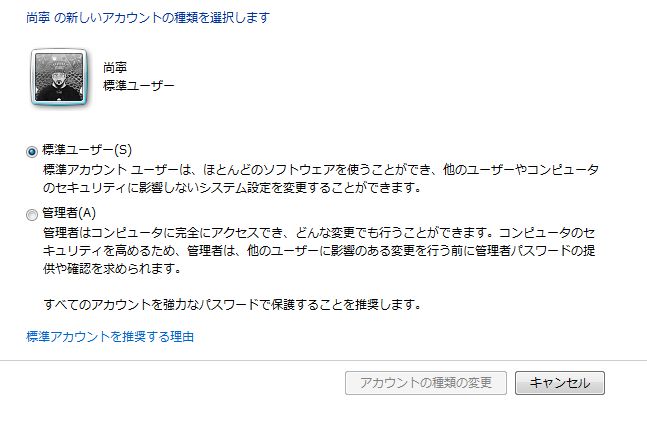琉球国にイスラム教が普及する可能性は1511年(永正8)にポルトガルがマラッカを占領し事実上南方との交流が制限されたことで限りなくゼロに近づきます。1609年(慶長14)には島津氏による琉球侵攻及び江戸幕府による海禁政策によってイスラム教はおろか新しい宗教が普及する可能性もゼロになります。
明治の世になってようやく信仰の自由が保障され、その結果禁教扱いだった浄土真宗やキリスト教が普及しますがこの期に及んでもイスラム教は蚊帳の外です。大正→昭和→平成の世を経ても普及する様子はありません。
イスラム教圏ですらアメリカナイズされつつある今日、沖縄に於いてイスラム教が普及する可能性はゼロと言わざるを得ません。1372年から1511年の交易時代に布教のタイミングを逃したことがすべてです。趣味や学問として研究することはあってもイスラムの教えに帰依する沖縄県民は今後出現しないと断言せざるを得ません(終わり)。