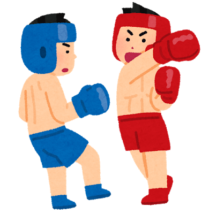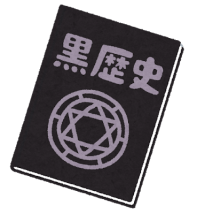今回は復帰後の沖縄において実際にあった反自衛隊闘争について言及します。いまではありえないことですが、我が沖縄において自衛隊所属のスポーツ選手は沖縄代表として国体に派遣されることはありませんでした。その前例になった事件については後日説明しますが、昭和52(1977)年10月開催の第32回国体秋季大会(青森県)で初めて自衛隊所属の選手が国体に派遣されます。
シリーズ
黒い祖国復帰運動
今回もアメリカ世時代の新聞ネタをもとに記事を作成しますが、昭和39(1964)年8月7日付琉球新報夕刊1面に”ものくゆすどわが御主”というタイトルで祖国復帰に関する世代間対立のコラムが掲載されていました。
学びの国…がぴったり
本日もブログ主は沖縄県立図書館を訪れて史料チェックをしていましたが、その中で極めて興味深い記事を発見しました。それは昭和52(1977)年8月29日付琉球新報5面に「学びの国…がぴったり」と題したとある国の教育事情についての記事です。
平和の擁護 – 原子戦争反対、沖縄の原水爆基地化反対
前回の記事においてブログ主は沖縄原水協の分裂騒動について言及しました。なぜこの記事に関心をもったかと言うと、実は以前に沖縄人民党第七回党大会(1956年1月22日)および民連選挙の綱領を見たことがあるからです。
たとえば沖縄人民党第七回党大会の綱領には
不屈の精神とは言うけどさ……
本日沖縄県立図書館で琉球新報の記事をチェックしていたところ、昭和39(1964)年7月21日付琉球新報朝刊1面に「原水協、分裂状態に」と題した沖縄原水協の分裂騒動についての記事が掲載されていました。ブログ主は原水協(原水爆禁止日本協議会)など日本の原水爆禁止運動については詳しい知識はありませんが、それでも記事内に気になる記述がありましたので当ブログにて紹介します。
【急募】琉球藩の二枚舌交渉を擁護する方法 – その5
(続き)明治8年7月の明治政府による御達書(行政命令)に対する琉球藩の交渉ですが、当初は個別案件に対して受けるか否かの話でした。たとえば刑法習得のため学生派遣は可、軍隊駐留は条件付きで可、清国との関係断絶や日本の年号統一、あるいは藩政改革は拒否などで、ここまでは明治政府から派遣された委員たちも想定の範囲内でした。
【急募】琉球藩の二枚舌交渉を擁護する方法 – その4
前回の記事で簡単ながら明治政府と琉球藩との国家間の違いについて説明しました。これだけ認識の違いがあると交渉がすれ違いになるのもしょうがない部分はありますが、それでもやってはいけないことはあります。
明治政府による琉球藩への行政命令(御達書)の中の清国との関係断絶に関して、同年9月4日に琉球藩王尚泰の署名付の公式回答を紹介しますが、これは前回記事で紹介した同年9月3日の回答の斜め上をいく酷い内容となっていますので読者のみなさん心してご参照ください。
【急募】琉球藩の二枚舌交渉を擁護する方法 – その3
今回も『琉球見聞録』をベースに明治8年9月における琉球藩の対日交渉について言及します。前回の記事で同年9月3日(新暦)の琉球藩王尚泰署名の公式回答が松田道之を怒らせたことを説明しましたが、なぜ琉球藩が「日清交渉において進貢中止が決定後、清国より正式な外交文書で進貢中止の通達があったのちに(明治政府の達書を)お請けします」なんて回答をしたのか、ブログ主なりに考えてみたところ、以下の仮説に行き着きました。
【急募】琉球藩の二枚舌交渉を擁護する方法 – その2
今回はひさびさに真面目な歴史記事を掲載します。以前、『【急募】琉球藩の二枚舌交渉を擁護する方法 』と題した記事をアップしましたが、ブログ主も沖縄県民としてご先祖さまのやらかしに対してとかくのツッコミはいれたくないのです。だがしかし明治8年以降の琉球藩の対日交渉をつぶさに観察すると、あまりの酷さに
ものくゆすど、わ御主
先日ブログ主は史料チェックのため沖縄県立図書館の郷土資料館でまったりと涼んでいました。その際に山里永吉先生*の著作を読んでいたところ、突っ込まざるを得ない記述があるのを発見しました。
せっかくなのでその部分をコピーして全文を書き写しました。読者のみなさん是非ご参照ください。
*山里永吉(ヤマザト・エイキチ:1902~1989)戦前・戦後を代表する文化人の一人。画家、作家、歴史家、陶芸家。琉球史劇「首里城明け渡し
突っ込まざるを得ない記事を紹介するシリーズ – やべーじじい発見
今回は沖縄ヤクザ関連の史料をチェックしているうちに発見した “カジマヤー” の記事を紹介します。昭和37(1962)年10月5日の琉球新報夕刊に前里宗快さん(97)のカジマヤーを祝う記事が掲載されていました。すごくいい話ですが、少しひっかかった部分があったので記事の一部を書き写しました。読者のみなさん是非ご参照ください。
*カジマヤー:数え年97歳のときに行われる長寿祝いで、旧暦9月7日に盛大に催されるのか慣例です。
【急募】琉球藩の二枚舌交渉を擁護する方法
今回は明治8年(1975年)に実際に起こった琉球藩の二枚舌交渉について言及します。事の発端は同年7月29日(新暦)に来琉した松田道之が通知した御達書の中にあった「清国との関係断絶」「日本の年号使用」そして「藩政改革」に対して琉球藩が難色を示したことです。
宮古島の惨状
今回は尾崎三良(おざき・さぶろう)関連の史料から宮古島に関する記述を紹介します。尾崎関連の史料は明治15年11月26日に山形有朋参議に提出した『沖縄県視察復命書』がよく知られていますが、今回は明治15年7月19日から9月26日までの滞在記(尾崎三良琉球行日記)を参照しました。
琉球王国時代の宮古島については人頭税に代表されるように「搾取された」イメージが強いのですが、実際の史料をチェックすると予想の斜め上を行く惨状であったと思わざるを得ません。本島出身者には心が痛む内容かと思いますが、こういう現実があったことは無視するわけにはいきません。読者のみなさん是非ご参照ください。
ウチナータイム
先日よりツイッターで話題になっている不良マンガ「東京から沖縄に転校してきた不良の四コマ」でいわゆるウチナータイムに言及している箇所がありました。ウチナータイムはウィキペディアにも登場する程のウチナーパワーワードですが、ウィキの説明はちょっと凝りすぎるところがありますので、わかりやすい例として斎湖 伴仗さんのツイッターを引用します。読者の皆さん是非ご参照ください。
自衛隊は招かざる客
前回の記事があまりにも反響を呼び過ぎたため、正直公開をためらいましたが、今回は昭和52年1月の自衛官成人式不招待問題の記事を紹介します。ちなみにこの問題は、昭和54年(1979年)から那覇市が成人式の主催を地区実行委員会に変更したことで解決します。つまり地区の実行委員会が成人式に自衛隊員を招待するようになったことで、那覇市長の事実上の敗北という形で決着がついたのです。