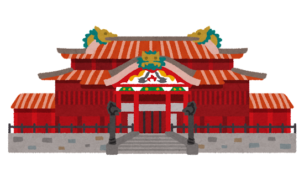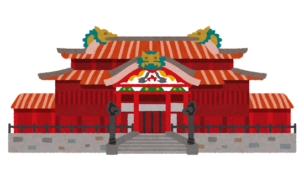ここ数日、SNSでのやり取りで色々思いつくことがあり、今回はとある呟きに対するブログ主の考察をまとめてみました。それは令和5年(2023)9月30日付のRobert Kajiwara氏(比嘉・梶原孝昌ロバート)の投稿ですが、「琉球独立国の再建、すべての琉球人・うちなーんちゅに平和と繁栄」と題し、琉球独立国の再建についての “お気持ち” が表明されていました。
シリーズ
過去の “自分” が襲い掛かる恐怖
ここ数日、ブログ主はたまっていた新聞史料をチェックした際に、偶然にも興味深い記事を見つけました。令和6年11月30日付沖縄タイムス23面に「SNS心得は自己肯定感」と題し、スマートフォンアドバイザーのモバイルプリンスさんが中学生を相手に講演した小さな記事ですが、非常に参考になる内容でしたので全文を書き写しました。
彼に関しては過去に一度取り上げましたが、「専門家」としては一目置かざるを得ない人物なので、興味深く記事を読ませていただきました。読者の皆さん、是非ご参照ください。
俺が調子に乗ってライトなシージャネタを紹介する記事
本日はクリスマスということで、今年も恒例の風俗記事をアップといきたいところですが、今月22日の名護市議のやらかしがあまりにも強烈すぎたので、とりあえず復帰前後のシージャネタでお茶を濁します(理由:勝てる気がしないから)。
そのシージャネタも去年紹介した “中絶模合” に勝るレベルはなかなかありませんので、取り急ぎ軽めのネタでまとめてみました。読者のみなさん、是非お愉しみください。
尚泰久王の謎
今回は、ももとふみあかりに関する人物として尚泰久王(1415~1460)の “謎” について考察します。彼は定説によると尚巴志(1372~1439)の五男で、越来の按司から第6代のりうきう国王に即位した人物です。そしてももとふみあかりの実父としても知られていますが、彼にはこれまで解せなかった謎があります。それは神號が2つあることです。
昭和のりうきう(民度編)
以前、ブログ主は琉球新報特集記事「婦人の見た中国」(全6回)の全文およびまとめページを当運営ブログにて公開しました。昭和のりうきう知識人のちうごく感が伺える貴重な内容ですが、ただし現代人から見ると “お花畑” に思えるのも無理はありません。
昭和のたくましいおばーたち – 偉人編
前に紹介した、復帰後の国際通りの夜店で働く女性の記事が思いのほか好評を得ましたので、今回も調子に乗って昭和のたくましいオバーの記事を紹介します。昭和49年10月6日付琉球新報朝刊に、ある老人ホームの嘱託医の記事が掲載されていましたが、何とその医者の名は千原繁子さん(1898~1990)。ご存じの方もいらっしゃるかと思われますが、我が沖縄の歴史における初の「女医」として知られる偉人中の偉人です。
昭和のたくましいおばーたち(1)
今年は我が沖縄が本土復帰して52年目になりますが、ブログ主は試しに復帰後の沖縄社会の史料、特に新聞記事を重点的にチェックしてみたところ、非常に興味深い高齢者に関する記事を見つけました。
尚泰候の決断 – 番外編
これまで「尚泰候の決断」と題して、真面目な歴史記事を4回に分けて配信しましたが、今回は番外編としてりうきうの王家・王族、そして上級士族の一大特徴である “二重思考” について言及します。
尚泰候の決断 その4
(続き)前回までに尚泰候の藩王時代の騒動についてやや詳しく説明しましたが、その出来事によって彼が決断できない “為政者” に成り下がった件を理解いただいた上で、明治29年(1896)の “決断” にいたった背景についてブログ主なりに言及します。
尚泰候の決断 その3
(続き)明治8年(1875)年9月7日(新暦)、明治政府、とくに来琉した松田道之との交渉過程で「事ここに至っては」の状況であると判断した藩王尚泰は、三司官に対し明治政府からの「御達書」を遵奉する旨を伝え、三司官側からも特に反対意見がなかったため、那覇へ使者を遣わす手はずを整えるよう命じます。
この日の騒動については「琉球見聞録」と「尚泰候実録」では一部記述が異なる部分はありますが、ブログ主なりにまとめてみると、
尚泰候の決断 その2
(続き)今回は尚泰候の決断について、予備知識として藩王時代の明治8年(1875)9月(新暦)の騒動について言及します。彼は有事の際に断固たる判断ができない為政者のイメージが強いのですが、実は例外的に “決断” を下したが故に酷い目に遭いかけた痛い過去があるのです。
その後の藩王は廃藩置県の明治12年(1879)まで毛利敬親の如く “そうせい候” の状態になってしまいますが、ブログ主はそれ故に明治29年(1896)の「断固たる決断」には強い違和感を覚えるのです。
尚泰候の決断 その1
先日ブログ主は過去記事をチェックした際に、史料の読み違いによる記述ミスに気が付いたので、その点についての説明と、それに関して “尚泰候の決断” と題した新たな記事を公開します。
皇室と沖縄社会とタブー
今月12日ごろ、「沖縄青年同盟」の活動家の訃報ニュースが県内2紙に掲載されていました。彼らが起こしたとされる「国会爆竹事件」など、彼らの活動そのものには「今更どうでもいい」との感しか湧きませんが、沖縄2紙がわざわざ活動家の訃報を、しかも追悼文(沖縄タイムス)まで掲載していた事実には強い興味を覚えました。
あいろむノート – 方言札(7)
(続き)6回にわたって掲載しました “あいろむノート – 方言札” シリーズも、今回のまとめを以て〆ますが、これまでの当ブログにおける説明にて「方言札」は日清・日露戦役後に新しい時代に適応すべく、教育現場から誕生した件についてご理解いただけたかと思われます。
あいろむノート – 方言札(6)
(続き)今回は、アメリカ世時代の教育現場における「方言札」の運用について、新崎盛暉(あらさき・もりてる)先生の証言を紹介します。戦後の方言札運用について、ブログ主も伝聞ベースでは知ってましたが、それでも新崎先生の証言内容には驚きを覚えましたので、証言全文を紹介します(以下証言)。