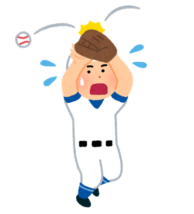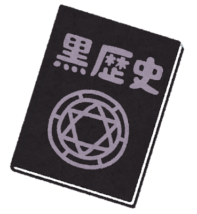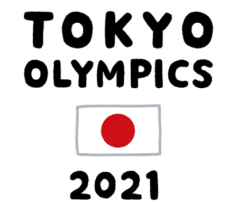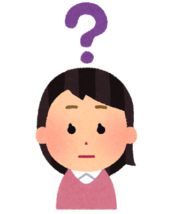本日付沖縄タイムス22面に “スポーツ指導 / 私の提言” と題したコラムが掲載されていました。執筆者は新里紹也さん(元プロ野球選手)ですが、説得力が半端ない内容で、速攻で全文を書き写しました。
コラム
個人への配慮が足りませんでした(棒)
今月11日付沖縄タイムス26面に “「あなたのまわりの森発言」募集 / タイムス社” と題して、幅広く意見を募集する記事が掲載されていましたが、即ネット上で炎上騒ぎとなり、同社は公式 Twitter で謝罪する顛末となりました。
森発言考
今月3日、日本オリンピック委員会(JOC)の臨時評議会での森喜朗会長(当時)の発言が絶賛炎上したのは記憶に新しいのですが、ブログ主はこの案件にひっかかるものがあり、さっそく発言全文を写本しました。
宜野湾民の俺が調子に乗って浦添市長選について語ってみた件
今回は当ブログにしては珍しく時事ネタを提供しますが、先日8日に投開票が行われた浦添市長選挙について言及します。既報でご存じかと思われますが現職のまつもと哲治候補が1万票の差をつけて伊礼ゆうき候補(無所属)に勝利しました。
自滅の刃 – その2
(続き)前回の記事で鬼滅の刃の人気の秘密についての小学生女生徒の投稿に対する返信について言及しましたが、実はこの後も返信がありました。〆は2月1日付琉球新報8面に掲載された石原昌家さん(沖縄国際大学名誉教授)の投稿です。
自滅の刃 – その1
令和03年1月12日付琉球新報8面の “声” のコーナーに大人気漫画 “鬼滅の刃” についての小学生女生徒からの投稿があり、その後の展開がじわじわきましたので、関連する投稿を全部を書き写してきました。
歴史は繰り返す。
11年前の平成22(2010)年1月24日行われた沖縄県名護市長選挙の結果、普天間基地の辺野古移設に反対する稲嶺進候補が当選したことに関して、同月27日に内閣に提出された質問主意書が実に興味深いので一部紹介します。
コザ暴動の教訓 – 建前と本音の乖離
“「建前」は必要なものだ。誰の中にも潜む差別、怒り、ねたみを「本音だから」とそのままぶちまければ、やがて暴力が社会を破壊する。トランプ氏の「本音トーク」4年間の帰結を見れば、はっきりしている。”
下地幹郎氏が “結果を出す政治” を実践した結果
先日行われた宮古島市長選挙で現職が落選し、ひさびさにオール沖縄陣営が湧いていますが、それに絡んでブログ主は “下地幹郎氏” のこれまでの “実績” で打線を組んでみました。政局ネタ好きの読者のみなさん、是非ご参照ください。
俺が調子に乗って昨今のマスコミ不信について解説するよ
平成28(2016)年5月からスタートした当運営ブログですが、その際に記事作成のため数多くの新聞記事を参照してきました。必要に応じて OneNote などの保存ツールに記事を写本してきましたが、最近になって気が付いたことがあります。それは昨今の(たとえば)ネット上における著しいマスコミ不信は “起こるべくして起こった” ということです。
コザ暴動について – 糸満主婦れき殺事件の余波その2
(続き)前回、昭和46(1971)年9月18日に糸満で起こった米兵による主婦れき殺事件の軍事裁判の経緯について言及しました。無罪判決にいたるまでの流れを調べると、当時の琉球住民たちが激怒するのも無理はない話ですが、だがしかし “無罪判決” は近代デモクラシーにおける裁判制度では十分にありえるのです。
令和03年度を迎え、各所でうーとーとーして来たお話
あけましておめでとうございます。当運営ブログも今年5月で5周年を迎え、目標の1000記事配信まであと58回となりました。これもひとえに読者の皆様のご贔屓の賜物でありまして、厚く感謝申し上げるとともに、今年も皆様に楽しんでいただけるよう調子に乗った記事を配信する所存です。今年度もどうぞよろしくお願いいたします。
コザ暴動について – 糸満主婦れき殺事件の余波その1
(続き)前回は昭和43(1968)年12月に誕生した屋良朝苗政権に対する琉球住民の不満がコザ暴動の “遠因” であることを言及しましたが、今回は “近因” である米国民政府に対する爆発的な不満、その導火線になった昭和45(1970)年9月18日に糸満で起きた米兵による主婦れき殺事件について説明します。
大弦小弦の凋落
今月28日の沖縄タイムスをチェックした際に、じわじわくるコラムが目に留まりましたので速攻で全文を書き写しました。ところで沖縄タイムスのコラム “大弦小弦” はいつの間にかプラス版(WEB)では “鍵付き” になって読めなくなっています。ただし琉球新報の “金口木舌” はデジタル版でも全文公開されています。
コザ暴動について プロローグ
12月に入ってから、我が沖縄のマスコミでは “コザ暴動” に関する報道数が著しく増えています。事件発生から今年で50年の節目にさまざまなイベントも開催され、事件に関する関心も高まっているように見受けられます。