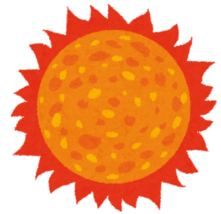
前回までアップした二代目聞得大君の記事に関連して、ブログ主は峯間聞得大君(と思わしき)オモロを複数チェックしました。今回は、その過程で改めて気づかされた古りうきうの為政者たちの宗教観の変遷について調子に乗って言及します。
ちなみに、古代における我がりうきうの最高神は “日神(てだ)” であり、地上の権力者は日神の子孫であるとの “日子(てだこ)思想” によって統治権を行使してきたことはよく知られています。
わかりやすい例として、1260年ごろにりうきうを統一したとされる英祖(えいそ)の神號は「日子(Tidaku)」であり、東恩納寛惇先生の論文「琉球人名考 / 第七章 王の神號」によると、日神に関する神號の例として「日子、君日、日始、日豊操、日賀末」を挙げています。
ここで参考までに、“日子思想” とは鳥越憲三郎著『おもろさうし全釈』に登場する用語で、おもろさうし巻1の2の解説によると、
あらゆる民族の統治者と同じく、琉球でも地上最高の主権者である城主や国王は、宇宙の至上神である日神と同格ないし同質のもの、或いはその子孫と見られていた。したがって、国王は日神の守護を直接に受けられるとともに、その代弁者として国土の統治権を日神から委譲されたものとも信じられていた。この神託は、国王の統治権が日神に由来する絶対的なものであることを、一般人民に対しても示す大切な役目ともなったであろう。また国王みずからにとっても、日神が直接守護されることの自信を抱き得たものといえよう。
(中略)「てだ」tidaは太陽ならびに日神の称である。これは「てり」〔照り〕に、人などをその性質や姿によって呼ぶときに用いる接尾辞の「や」のついたもので、この「照りや」tiri – jaの語尾が長音可してtiraaと訛ったものである。離島では今でもその発音であるが、首里放言ではラとダの転訛によって、Tidaとなったものである。したがって「照るもの」の意で、太陽ならびに日神の称として用いられる。なお「てだ」は「神てだ」・「てだこ」という表現もとられる。またこの語は、城主や国王が日神の子孫であるという日子思想から、城主や国王の称としても用いられ、その用例を多く見出すことができる。
とあり、古代の為政者は日神から統治権を委譲されたとの確信のもと、権力を行使していたことが伺えます。
ここで興味深いことに、りうきう国初代の国王とされる「そんとん(舜天)」には神號が伝わっていません。ただし、その存在は16世紀上の史料で確認ができ、たとえば尚清王(在位1527-1555)は「そんとんより、このかた、21代の王の御位」として、尚寧王(1589-1620)は「そんとんよりこのかた、24代のわうの御くらゐ」として神號を授かっております。
※尚清王の神號である天続之按司(てんつぎのあじ)とは、「そんとんより続く(天続)日神の末裔である按司(王)」の意
※尚寧王の神號である日賀末按司添(てだがすえあじおそい)とは、「日神の末裔である按司を統べる王」の意。
なぜ「そんとん」に神號が伝わってないのか、今となっては確認する方法はありませんが、残された数少ない史料から、16世紀の為政者たちは、彼を “日神の子” と考えていたのは間違いありません。
ところが、17世紀になると「そんとん」の出自が、『中山世鑑』などの史書によって源為朝の息子に代わります。ご存じのとおり為朝は日神の子ではなく、清和源氏の末裔で日本史のスター的存在です。羽地朝秀が「日琉同祖論」を展開するため、彼を為朝の息子として記述した可能性が高いのですが、いずれにしても慶長の役(1609)の敗戦により、為政者たちによって歴史が書き換えられたわけです。
それによって、為政者たちの宗教観念も変化してしまい、統治権の根拠が「日神の末裔」から「薩摩の承認」に代わってしまったのです。
大雑把に説明しましたが、17世紀初頭の戦争の結果、歴史が一部書き換えられたのは残念としかいいようがありません。なお、参考までに、舜天即位の1187年を琉球国の始まりと見做している “りうきう独立芸人” さんは、「そんとん」の出自についてどのような見解をお持ちか聞いてみたいと余計なことと考えつつ、今回の記事を終えます。