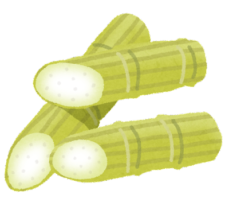
今回は当運営ブログらしく?真面目な歴史ネタをアップします。1623年に我が沖縄において製糖業が始まったとされますが、興味深いことに大城立裕先生は著書『沖縄歴史散歩』の中で “これが沖縄にとって幸せであったか不幸であったかは決めがたい” と言及しています。
同著89ページによると、
島津藩はこれに眼をつけ、やがて米粟穀の貢租を砂糖で代納してよいと定めるのだが、ついには砂糖が貢租の主座を閉め、島津藩の財政の救世主になる。同時に沖縄の農民は砂糖生産のための奴隷のようになっていく。沖縄の郷土史家、比嘉春潮氏の調べによれば、近世から近代にかけて、遊郭の娼婦数について出身地別に統計をとってみたら、土地生産力が高く砂糖生産の高い地方ほど女子の身売りが多いことが分かったという。砂糖生産の儲けが貢租負担に追いつかなかったということであろう(下略)
とあり、17世紀以降の尚家が支配したりうきうにおいて、砂糖生産を割り当てられた地区(主に島尻地方)は悲惨な状況に置かれていたことが窺えます。ちなみに今回は砂糖取引における悪名高い “砂糖前代(さとうまえだい)” について言及しますが、砂糖前代とは糖商(薩摩出身の商人)が農民に資金を貸し付けて格安で黒糖を仕入れるシステムで、沖縄大百科事典によると、
砂糖前代による取引方法は次のとおりである。➀前代を貸す時点で1挺の相場より2,3円安く価格を決めて金を貸し、その値で砂糖を引き取る、➁相場より安く貸し元利とも砂糖で生産する、➂前代を貸して利息を砂糖で取る。砂糖は確実に売れる商品であったから前貸のよい対象になった。
とあります。大雑把にまとめると農民にとっては手っ取り早く現金を得る機会も、砂糖商人に格安で砂糖を引き渡さざるを得ない貸付なのです。現代の基準から見ると商人による農民に対する搾取以外何者でもありませんが、実は商人側にとっても格安で砂糖を仕入れないといけない事情があったのです。試しに砂糖商人の視点から当時の黒糖の仕入れ、輸送、販売についてブログ主なりに説明します。
まず、黒糖取引は仕入れと運搬が大変な作業なのです。黒糖の取引は村単位で行ないますが、砂糖商人は現地に出向いて数挺単位で取引します。ちなみに黒糖1挺は大正時代まで特に基準はありませんが、(推測すると)砂糖1樽=黒糖1挺=72キログラムぐらいなので、つまり数挺単位の黒糖を那覇の倉庫まで人力で輸送するわけです。これだけでも大変な労力と賃金が発生します。
那覇の倉庫での黒糖の保管された黒糖は、当然船に積み込む必要があります。が、実はこの作業が最難関で、当時の那覇港は大型船が接岸できないため、小舟を利用して大型船にいちいち乗せ換えないといけません。もちろん人力です。つまり黒糖販売は、その過程における砂糖樽の輸送と管理に人件費が嵩んでしまうわけです(もちろん人件費は今も昔も簡単にはケチることができません)。
しかもそれだけでなく、19世紀までの砂糖取引は那覇ではなく大阪で “品質鑑定” をして始めて全国の市場に出回りますので、仮に当地で「低級」と判断されたらそれだけ儲けが減るわけです。たしかに黒糖は “確実に売れる商品” ですが、市場に出すまでの手間がものすごくかかるため、砂糖商人側としてはできる限り安く仕入れたいとのインセンティブが働きます。その結果として誕生したのが “砂糖前代” という貸付方法なのです。
砂糖前代は手早く現金が得られるために農民にとっても “必要悪” の貸付方法ともいえますが、こんなやり方を続けると当然ながら黒糖生産地が疲弊しますし、その結果、砂糖生産地の高い地域ほど女子の身売りが多かったという悲惨な結果になったのも頷ける話です。参考までに黒糖取引において生産者が有利な立場になったのは大正時代に県が産聯(保証責任沖縄信用販売購買利用組合聯合会)を結成して以降なのです。
なお、19世紀までの砂糖取引のおける(極端なまでの)買い手有利の状況を把握しながらも、
首里王府が積極的に砂糖前代対策を講じたという話は寡聞にして存じません。
ブログ主は砂糖取引におけるりうきうの闇の深さに愕然としつつ今回の記事を終えます。