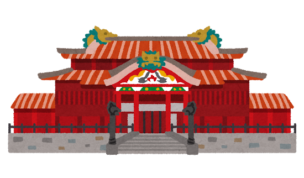
今回はちょっと真面目なコラムを掲載します。慶長の役(1609)から明治12(1879)年の廃藩置県までの琉球国をふりかえると、実は何度か王家存続の危機があり、その点について言及します。
慶長14(1609)年の薩摩入りによって、時の王尚寧が薩摩によって本土に連行されたことはよく知られています。慶長16(1611)年に彼は無事帰国できましたが、もしも本土で亡くなってしまった場合は王家存続の大ピンチに陥ること確実だったのです。その理由は尚寧に嫡子がいなかったからです。戦に負けて国王が連行という一大危機を乗り越えた琉球国ですが、その後も王家存続の危機がたびたび起こります。
次のピンチは寛永21(1644)年の大明の滅亡で、尚賢王4年にあたります。それだけならまだしも正保4(1647)年に尚賢王が22歳の若さでなくなります。しかも世継ぎがいなかったのです。このピンチに際し、尚賢王の弟尚質が王位を継ぎ、(詳細な説明は省きますが)明から清へ “鞍替え” することで王家存続の大危機を乗り越えます。
1673年に中国大陸で三藩の乱が起こったときも、王府は清につくか、新興勢力(靖南王耿精忠)につくかで苦悩します。幸運にも靖南王が自滅したので、何事もなかったかのように清国とこれまで通りの関係を維持することに成功しますが、中国大陸の動乱に危うく(薩摩ともども)巻き込まれそうになった事実は注意すべきです。
時代が下って19世紀になると異国船が来琉します。王府および薩摩は異国船は受け入れない方針でしたが、嘉永6(1853)年にペリィ提督によってその禁が破られます。そして翌年に琉米修好条約を結ぶことで、これまでの海禁政策に終止符が打たれます。いわば外圧によって国策を大幅に変更せざるを得なくなり、その後牧志・恩河事件という異質極まりない内紛も起こりますが、結果として王家の存続には大きな影響を及ぼさなかったのです。
ほかにも慶長の役から270年間を振り返って何度か経済危機あるいは疫病や天変地異などの危機的状況が発生しますが、それでも王家の統治が続きます。首をへし折られそうな出来事が続いたにも関わらずなぜ尚家は琉球を支配し続けたのか。その理由は、上記のイベントが結果として “統治の根幹” を犯さなかったからなのです。
では “統治の根幹” とは何か。それは誤解を恐れずにハッキリ言うと、
日支両属こそ王家存続の最大要因
だったのです。日支なんて用語を使うと「差別だー」と怒る読者もいるかもしれませんので、「薩摩の島津家と中国大陸の皇帝と両方と付き合うことが尚家存続の必要十分条件だ」と言い換えましょうか。つまり “両属” が最大のカギで、上記の案件はこのタブーに触れていないのです。
その証拠に明治5(1872)年に明治天皇より琉球藩に封じられて、その3年後に明治政府から清国との関係断絶を通達された際の国王尚泰および藩首脳のパニックぶりをチェックすれば理解できるはずです。あれほど強固だった尚家の支配が明治8(1875)年の通達からたった4年で廃藩置県(つまり王家廃絶)に追い込まれたのです。
この事例から “くにが滅ぶ” プロセスを読み取ることができます。つまり
・為政者にとって想定外の事態が発生する。
・それが “統治の根幹” を揺るがす事態に発展する。
・その結果政治が機能しなくなり、最終的に崩壊。
という流れです。この点は極めて重要だとブログ主は判断してますので、今回あえて言及したのですが、本来なら琉球独立論者が考察する内容なんですよね。つまり日本が沖縄を統治する正統性(根幹)はなにか、そしてそれをどのように崩すかを徹底的に追求する必要がありますが、己に都合のいいように歴史事例をつまみ食いする芸人たちには無理な話かなと思いつつ、今回の記事を終えます。