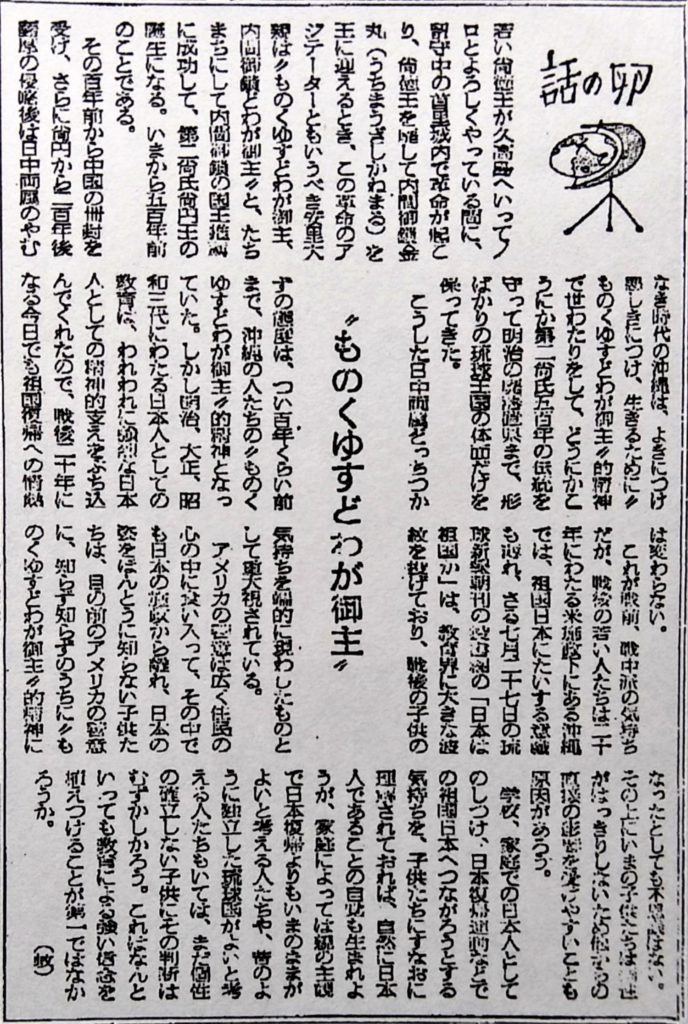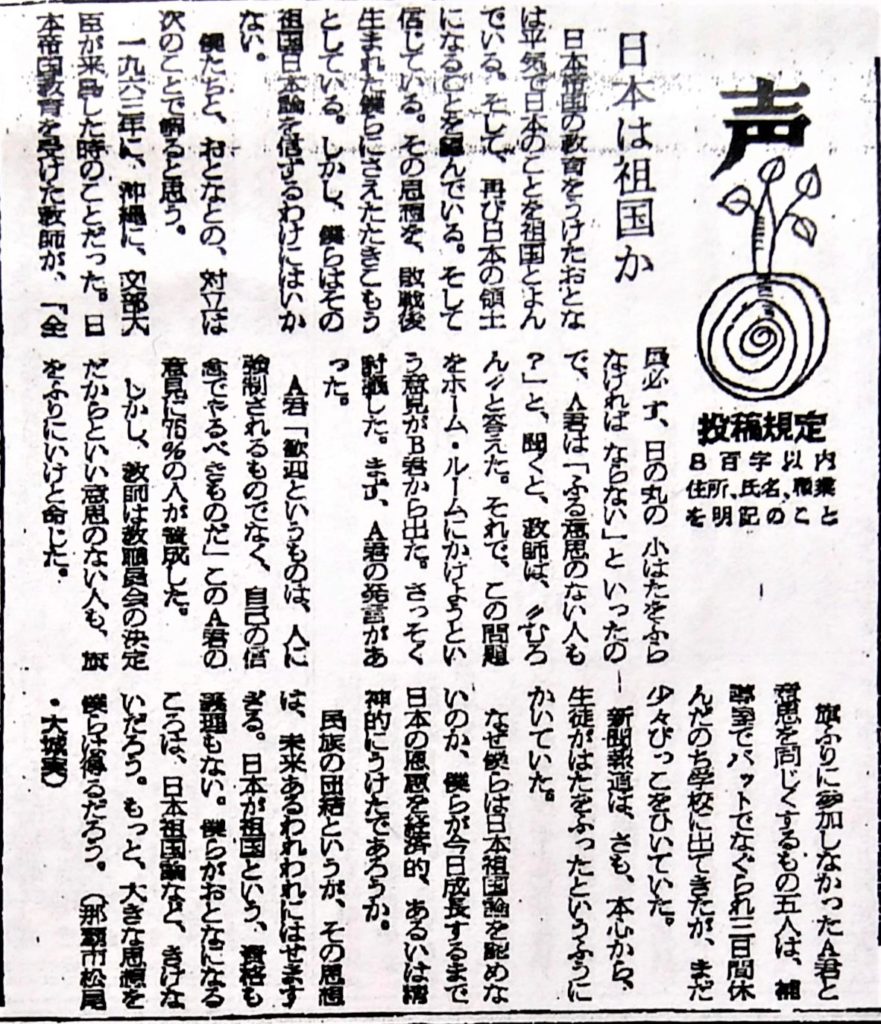今回もアメリカ世時代の新聞ネタをもとに記事を作成しますが、昭和39(1964)年8月7日付琉球新報夕刊1面に”ものくゆすどわが御主”というタイトルで祖国復帰に関する世代間対立のコラムが掲載されていました。
先に結論を申し上げると、日本が祖国であることに対する世代間の認識は異なるも、教育による強い信念を植え付けることで克服はできるだろうという内容です。コラム全文を書き写しましたので読者のみなさん是非ご参照ください。
”ものくゆすどわが御主”
若い尚徳王が久高島へいってノロとよろしくやっている間に、留守中の首里城内で革命が起こり、尚徳王を廃して内間御鎖金丸(うちまうざしかねまる)を王に迎えるとき、この革命のアジテーターともいうべき安里大親は”ものくゆすどわが御主”と、たちまちにして内間御鎖の国王推薦に成功して、第二尚氏尚円王の誕生になる。いまから五百年前のことである。
その百年前から中国の冊封を受け、さらに尚円から二百年後薩摩の侵略後は日中両属のやむなし時代の沖縄は、よきにつけ悪しきにつけ、生きるために”ものくゆすどわが御主”的精神で世わたりをして、どうにかこうにか第二尚氏五百年の伝統を守って明治の廃藩置県まで、形ばかりの琉球王国の体面だけを保ってきた。
こうした日中両属どっちつかずの態度は、つい百年くらい前まで、沖縄の人たちの”ものくゆすどわが御主”的精神となっていた。しかし明治、大正、昭和三代にわたる日本人としての教育は、われわれに強烈な日本人としての精神的支えをぶち込んでくれたので、戦後二十年になる今日でも祖国復帰の情熱は変わらない。
これが戦前、戦中派の気持ちだが、戦後の若い人たちは二十年にわたる米施政下にある沖縄では、祖国日本にたいする意識も薄れ、さる七月二十七日の琉球新報朝刊の投書欄の「日本は祖国か」は、教育界に大きな波紋を投げており、戦後の子供の気持ちを端的に現したものとして重大視されている。
アメリカの善意は広く住民の心の中に食い入って、その中でも日本の施政から離れ、日本の姿をほんとうに知らない子供たちに、知らず知らずのうちに”ものくゆすどわが御主”的精神になったとしても不思議ではない。その上にいまの子供たちは個性がはっきりしないため親からの直接の影響を受けやすいことも原因があろう。
学校、家庭での日本人としてのしつけ、日本復帰運動などでの祖国日本へつながろうとする気持ちを、子供たちにすなおに理解されておれば、自然に日本人であることの自覚も生まれようが、家庭によっては親の主観で日本復帰よりもいまのままがよいと考える人たちや、昔のように独立した琉球国がよいと考える人たちもいては、まだ個性の確立しない子供にその判断はむつかしかろう。これはなんといっても教育による強い信念を植えつけることが第一ではなかろうか。(蚊)
引用:1964年8月7日付琉球新報夕刊1面 – 話の卵
世代間対立はよくある話ですので、戦前・戦中の教育を受けた世代と戦後アメリカ世時代の教育を受けた世代では”日本”に対する認識が異なるのも当然といえば当然、そして教育によって世代間対立を克服しようという考え方も日本式教育を受けた世代らしい発想といえます。
問題は現場でどんな教育を行っていたかですが、上記コラムに記載があった同年7月27日付琉球新報朝刊の投稿の全文を掲載しますので、読者のみなさん心してご参照ください。
日本は祖国か
日本帝国の教育をうけたおとなは平気で日本のことを祖国とよんでいる。そして、再び日本の領土になることを臨んでいる。そして信じている。その思想を、敗戦後生まれた僕らにさえたたきこもうとしている。しかし、僕らはその祖国日本論を信ずるわけにはいかない。
僕たちと、おとなとの、対立は次のことで解ると思う。
一九六三年に、沖縄に、文部大臣が来島したときのことだった。日本帝国教育を受けた教師が、「全員必ず、日の丸の小はたをふらなければならない」といったので、A君は「ふる意思のない人も?」と、聞くと、教師は”むろん”と答えた。それで、この問題をホーム・ルームにかけようという意見がB君から出た。さっそく討議した。まず、A君の発言があった。
A君「歓迎というものは、人に強制されるものでなく、自己の信念でやるべきものだ」このA君の意見に75%の人が賛成した。
しかし、教師は教職員会の決定だからといい意思のない人も、旗をふりにいけと命じた。
旗ふりに参加しなかったA君と意思を同じくするもの五人は、補導室でバットでなぐられ三日間休んだのち学校に出てきたが、まだ少々びっこをひいていた。
新聞報道は、さも、本心から、生徒がはたをふったというふうにかいていた。
なぜ僕らは日本祖国論を認めないのか、僕らが今日成長するまで日本の恩恵を経済的、あるいは精神的にうけたであろうか。
民族の団結というが、その思想は未来あるわれわれにはせますぎる。日本が祖国という、資格も義理もない。僕らがおとなになるころは、日本祖国論など、きけないだろう。もっと、大きな思想を僕らは得るだろう(那覇市松尾・大城実)
引用:1964年7月27日付琉球新報5面より抜粋
どこから突っ込んでいいかわかりませんが、昭和39年当時は少年犯罪の増加や暴力団抗争などで社会全体に”暴力追放”の機運が高まっていた時期です。にもかかわらず教育現場では無理やり生徒を復帰運動に動員して、不服従の生徒には体罰の制裁を下しています。こんな調子ではいくら教師が「祖国復帰」と主張しても生徒は白けますし、「日本が祖国という義理も資格もない」と言いたい気分も分かります。
当時の新聞を参照して時代を感じたのが、8月7日付琉球新報コラムにおいて体罰に全く言及していないことです。それでいて教育によって”強い信念を植え付ける”と主張していますので、当時の教育現場で何が行われていたかを推知するに足る記事といえます。
アメリカ世時代の教育を受けた世代は”既存の権力、権威あるいは常識”に対して斜めに見る傾向があります。よくよく考えると個人の内面の良心を尊重せず、体罰も辞さない啓蒙主義的な教育を受けたらそうなってもおかしくありません。復帰運動は「全県民的な盛り上がり・・・」が沖縄の歴史におけるテンプレですが、実態は黒い部分を内包していたんだなと痛感したブログ主であります。(終り)