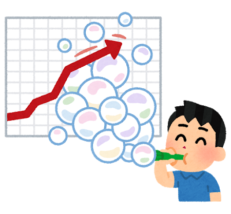
今回は琉球・沖縄の歴史において、ブログ主が思うに「忘れ去りたい記憶」について言及します。いわゆる黒歴史ですが、琉球・沖縄の歴史をふりかえるとそんなものは当然ながら掃いて捨てるほどあります。そのなかから今回は欧州大戦(第一次世界大戦)当時の好景気を取り上げます。
なぜこの案件が黒歴史扱いになっているかと言うと、
戦争は儲かる
という観念を当時の沖縄県人たちが共有することになったからです。この考えは決して間違いではないのですが、我が沖縄の歴史において戦争によって破滅した経験もありますから、どうしても戦争における”正の側面”には触れたくない心理があります。その結果、現代の歴史学において大戦ブーム(大正7,8年のバブル景気)は黒扱いになっている節があります。
ただしこのときの好景気は我が琉球・沖縄の歴史始まって以来の好景気ですので、当時の状況をチェックするのは歴史学にとって有益であることは間違いありません。ためしに昭和32(1957)年2月の琉球新報に大戦ブームに関する記事が掲載されていましたので全文を書き写しました。読者のみなさん、ぜひご参照ください。
【追記】この記事の面白いところは、バブル崩壊のプロセスにも言及していることです。あと補足として砂糖一丁はおおよそ120斤(=72㌔)の計算になります。
40年前の黄金時代 崎浜氏が語る…「大戦ブーム」
ビールで足を洗う – サラリーマンは洋服細民
最近の好景気(昭和32年)はともかく戦前では大正七、八当時が歴史始まつて以来の好景気といわれている。当事は物価が安い上に砂糖価格が高値をはつていたため特に農家はぜいたく三昧でくらし、ビールで足を洗うという位に異状な恩恵に預かつたようだが一方庶民は生活に困らないものの、特に安サラリーマンは農家から「洋服細民」といわれていたそうだ。
次は中金理事長崎浜秀主氏が語る当時の景気断片である。
○…戦前は大正七、八年ごろが景気の絶頂といえよう。あのころ砂糖は一丁(百斤詰)で五十円から七十円まで値上がりしたもので特に農村の景気は大したものだつた。商人は砂糖を売つても買つてももうかつていたから相当にかせいでいた。大阪や神戸からは船がくる度に砂糖商人がお金をどつさりもつて来て砂糖を買い占めてよく船積みして帰つたものだ。とに角当時は黄金時代といわれ沖縄に打寄せる波は黄金の波かといわれる位に形容されていた。特に農家はその恩恵に預かつている。それであの頃風を切つて歩いたのは農村の人と砂糖商人であろう。しかし一方官公吏や会社員などは生活にはさして不自由ではなかつたが、農村程に豊かではなかつた。
その頃農村の児童達は砂糖の値段と官公吏の俸給或は学校の先生の俸給と比較して学校の校長が特等で教頭が一分糖普通の教員は等外糖と批評し、校長と出合うとあいさつをした後から特等が行きおるという具合にね – 。又農村の人達も町の人をみると「洋服細民」と言つていた。これは洋服(服装)は奇麗だが家のくらしはきゆうきゆうであるという意味あいのものである。それで農民は当時の辻に行くとビールで足を洗うという位にぜいたく三昧であつた。また農村の青年たちは砂糖を二三丁那覇にもつて来てこれを売り、下駄をかつて床屋にでも行き、風呂でも入つて、それからゆうゆう辻に遊びに出かけるという調子だ。当時は何代酒代が一円でたらふく食べた上に女と遊びもできた位だから後は想像にまかそう。また当時は農村の人と砂糖商人と銀行員が料亭から大いにもてていた。その他の役場の人やサラリーマンは余りもてなかつたが、それでも一円位の出費は容易に出来たから外の人にも料亭や辻などには相当出入りが激しかつたと記憶している。
○…銀行員は現代も相当もてるようだが、金を扱う関係上この仕事だけは何時の世でももてる仕事だ。当時は銀行員に限つて白足袋をはいて一目でわかるような習慣であつた。銀行は那覇商業銀行、沖縄銀行、産業銀行、興行銀行に百四十七銀行支店、勧業銀行支店があり、預金も貸出も相当な数字をみせていたようだつた。主な顧客は勿論農村と砂糖商人である。地方に行くと洋服をつけた人にはあいさつなんかしない多分こんな連中と知り合うつても一文の利益もないという考えだつたかもしれないその代りハツピをつけた砂糖仲介人が通るとじいさんばあさんまでも丁寧にお辞儀をする位だつた。それに白足袋をはいた銀行員も拝まれた方でしょう。
○…物価も非常に安く泡盛が一合で十銭、そば一杯が四銭から5銭、映画観覧料金が五銭から十銭だつたと思う。その頃教員の給料は月平均三十円位だから砂糖一丁代にもならないわけだ、男の仕事は官吏や、教員、会社員の外にテンマもちとか、荷車もち、大工、左官などで女性で教員になるのは珍しかつた。女は殆ど家事であるが、商売は女性が多かつたようだ。当時は道ばたに立つて古着やら米、菓子、食物などを売つていたが、現代とは雲泥の差を生じている。
○…こういう話も当時はあつた。ある田舎の豪農であるじいさんが砂糖商人の招きで那覇の料亭にやつて来た。じいさんのみなりは貧弱でしかもハダシでしたが、それでもスタスタと料亭の玄関をまたぎ、部屋に入ろうとした。そのとき玄関にいたある芸者がそのじいさんにアンタなんかは台所から用件を済まして来なさいとこつびどく叱つたらしい、そこでじいさんはおとなしく台所に回つて行つたが、ちようど居合わせていた砂糖商人がこれをみて驚き、芸者を叱りとばしたようだ。あの人が今夜の主人公だと知らされたので、芸者連中はその老人に謝り、改めて玄関にお伴し足も洗つて部屋に丁重に案内したそうだ、その図はちようど水戸光圀公が諸国漫遊である田舎に立寄り、下郎共頭が高いぞとしつたする一場面のようでもある。
○…こうした景気は約二年程続いただろう。金料一丁の夢は何時までも続かなかつた。つまり砂糖の値が次第に下落し始めたのである。七十円から六十円、から五十円と急ピツチに下落、はては十円までになり下つたが、商人はきつと値上がりするだろうとなかなか砂糖を手離さず倉庫に入れたままではき出さない。そうこうしているうちに期日が立つて倉庫の砂糖はとけて流れ、倉庫には靴をはいて入れない状態となつた。それで砂糖商人が真先に破産してしまつた。続いてその商人の金を扱つていた金融機関が貸倒れでばたばたと倒れてしまう。それまで百万長者で威張つていたものがみる目も痛ましい程に無一文となつてしまつた。そこで他府県から来た商人達は店をたたんで次々に内地に帰り、当時の商人は現在おそらくいないと思う。なかには以前に自分が使つていた使用人に使われるような身の上になつた人もいると聞いた銀行は大正十四、五年頃地元銀行は合併して細々ながら経営は続いたようだ。農村のその後は余り知らないが恐らく豊かな生活ではなかつたと思う。
引用:昭和32(1957)年2月17日付琉球新報2面
